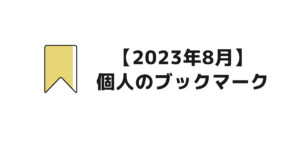【データマネジメント2025】我々はシステムを作ってるんじゃない、データを作ってるんだッ!!

2025年3月7日に開催された『データマネジメント2025』に参加してきました。
当日は8:30から始まって、18:30まで10時間(!)かけて11セッションを聴講。夕方には集中力も切れてぐったりでしたが、無事に完走を果たしました。
今回は印象に残った3セッションのメモと感想の記録です。
イベント概要
各セッションの感想の前に、簡単にイベントの概要にふれておきます。


| タイトル | データマネジメント2025 ~「Data as a Product」の時代へ~ |
|---|---|
| 日時 | 2025年3月7日(金) 8:30 – 18:30 |
| 会場 | ホテル雅叙園東京 |
| 受講料 | 無料 |
| 主催 | (一社)日本データマネジメント・コンソーシアム(JDMC) 株式会社インプレス |
タイムテーブルを見ると、1つのセッションが終わって次のセッションまで(基本的に)10分しかない。昼休みが見当たらないが、12:30-13:00はランチセッションとある。『ランチセッション ※軽食をご用意しております。』とあるから昼食の心配はしなくて良いのか…?
会場は”あの”雅叙園だし周辺の土地勘はないしで、当日の10時間をどう過ごすことになるのか、不安を抱えたまま東京には前日入りしました。
記憶に残った3つのセッション
以下が聴講した11セッションです。アンダーラインは特に印象に残った3つ。
| 8:30~9:20 | ビジネス成果にコミットするデータ部門の役割 ─ビジネスとデータの協創関係 |
|---|---|
| 9:30~10:40 | (主催者挨拶→基調講演1) 生成AIの技術的背景と将来展望 ─NIIのLLM-jp/LLM研究開発センターが目指すもの |
| 10:50~11:30 | 部門を跨いだデータ連携×人の知で実現する日本流製造DX ─「デジタルトリプレット」のすすめ |
| 11:40~12:20 | 古野電気が挑む「データの民主化」、その現在地 ─部門から全社へと広げる組織カルチャー改革 |
| 12:30~13:00 | (ランチセッション) データの“断絶の壁”を打ち破る! ロート製薬の先進事例に見る、データマネジメント基盤の本質 |
| 13:20~14:10 | (基調講演2) 「データを世界の共通言語に!」安川電機のDXビジョンと 日本の製造業の方向性、そして働き方改革 |
| 14:20~15:00 | データで切り拓く! デジタルバンク「みんなの銀行」の競争力を高めるデータマネジメント |
| 15:10~15:50 | 分析のことを考えながらシステムを作る ─モノタロウはどのようにデータメッシュを目指すのか |
| 16:10~16:50 | 今後求められる「製品」としてのデータとは? ─その価値創出を支える最新のデータ基盤技術 |
| 17:00~17:40 | 店舗出身者のIT部門が創造した アルペンの「内製化データマネジメント」の全貌 |
| 17:50~18:30 | 【MDMとデータガバナンス研究会】 Data as a Productへ!─悩みの原因も解決の糸口も 「すべての道はマスターに通ず!」 【生成AIによるデータ管理研究会】 思考連鎖、マルチモーダル、 そしてAIエージェント─生成AIとデータの関わりを追う研究会からの活動報告 |
古野電気が挑む「データの民主化」、その現在地 ─部門から全社へと広げる組織カルチャー改革
登壇者の”ノリ”が独特(関西ノリ?)で、導入の自虐と自慢と漫画ネタのノリについていけない時間はあったものの、「我われが作ってるのはシステムではなくデータ」という趣旨の発言は、この日最も強く印象に残りました。(タイトルにも使わせてもらいました)
セッションで紹介されていた『データドリブン思考』も購入したので、これから読みます。
セッションのメモ:
企業背景と基本姿勢
- 魚群探知機を世界初実用化した船舶電子機器メーカー
- 「システムではなくデータを作る」という考え方
- DX=データの民主化と定義
データ活用の考え方
- 二軸で分析:
- 縦軸:経営方針・文化醸成
- 横軸:実行力・企画力
- この枠組みでフルノの取組を整理
- 「データの民主化」の現状を具体的に共有
実行力を高めるための3ステップアプローチ
1. 世の中の動向を知る
- 16性格診断を活用
- 組織内の人材特性を把握
2. 現場を知る(3段階)
- 現場の人を知る
- 現場の実務を知る
- 現場の志を知る
3. 変革に対する「敵」を認識する
- 既得権益
- 保守主義
- セキュリティ
- いずれも「悪意なく善意から生じる抵抗」
4. 「味方」の可視化
- Tableauの利用データで協力者を特定
- データ活用に積極的な人材を見つける
5. 影響力を高める
- 組織内での変革推進力を構築
実践と成果
- ビジネス変革のスモールサクセス事例紹介
- 「データドリブン思考」(河本薫著)を参考文献として紹介
最終目標
- データ民主化の明確な目的は「収益の獲得」
- ツール導入ではなくビジネス成果を重視
参考:古野電機株式会社(企業Webサイト)
基調講演2「データを世界の共通言語に!」安川電機のDXビジョンと日本の製造業の方向性、そして働き方改革
午後の基調講演。導入で日本の国際競争力の低さから中国の話を経て企業紹介。経産省のDXレポートをク○だとけなし(気持ちはわかる)、その後で自社のDXやデジタル経営について語られてました。終始刺激的な言い回しを多用され、会場からは苦笑がもれる独特の雰囲気。
印象に残ったのは『DX推進の反省点と学び』の話。“コンサルタントを使うタイミングが早すぎた”と“現状で使えるツールは使い倒すべき”は、可能であればもう一度うかがいたい貴重な現場の声だと思いました。もし投影資料が配布されたら、ぜひ読み返したい。
セッションのメモ:
日本の国際競争力と労働環境
- 日本の国際競争力の現状:
- 男女雇用機会均等ランキングの低さ
- インターネット普及の遅れ
- 労働環境の特徴:
- 正規・非正規のバランスに課題
- 女性の就業率はG7内でも高い水準
- 高齢者が働く比率が突出して高い
- 日本人の労働時間は実は長くない(年間祝日G7最大)
- 提言:「同一労働同一賃金」より「同一成果同一賃金」が正しい
アジア競合国の動向
- 韓国と中国の急速な進展:
- 中国のEVタクシー普及
- 中国のバッテリーステーションの先進性
- 最新EVナビの導入状況
- 中国半導体産業の発展
安川電機の概要
- 「アイキューブメカトロニクス」を核とする事業
- 「お客さまを勝たせる」という企業理念
- YDX(安川のDX)以前の状況
DXへの取り組み
- 経産省DXレポートの影響:
- DXレポートで示された方向性(○○みたいなレポートと痛烈に批判)
- 「世の中のDXに惑わされない」という姿勢
- ソフトウェア=サグラダファミリア(いつまでも完成しない)
YDXビジョン
- 「世界の共通言語はデータ」という理念
- 「データを世界の共通言語に」というミッション
- 世界で共有するデータベースの構築
デジタル経営の実践
- 「1データ=1コード」の原則
- グローバルデータベースの構築
- YDX1とYDX2による全体最適グループ一体デジタル経営:
- YDX1:守りのDX(業務改革が目的)を優先実施
- 経営のコックピット化
- 働き方改革推進
- 連結決算2週間、四半期決算1週間への短縮
- YDX2:攻めのDX(顧客連携が目的)
- YDX1:守りのDX(業務改革が目的)を優先実施
DX推進の反省点と学び
- コンサルタントを使うタイミングが早すぎた
- 現状で使えるツールは使い倒すべき
- 先行している同業他社の話が最も参考になる
- トップ参加の推進会議は四半期に1度は必要
- 重要な発見:「投資金額と成否は比例しない。相関関係はない」
働き方改革の基本姿勢
- スローガン:
「各個人に合わせたスタイルで仕事をして、それを会社として公平に評価する」
今後の方向性
- 安川データベース(DB)の構築:
- 公開情報の統合
- 安川電機固有情報の管理
- YDX1,2の成果の活用
- 「データだけは自分(=会社)のもの」という考え方の徹底
参考:株式会社安川電機(企業Webサイト)
店舗出身者のIT部門が創造したアルペンの「内製化データマネジメント」の全貌
自分が聴講した中で一番勉強になったセッション。中小企業でも参考になる内容だと思います。4つのシステム区分、段階的なデータマネジメント、情シス・データ・ECを1部署とする体制、パートナーの分類いずれも改めて腹落ちするまで考えておきたいテーマ。
セッションのメモ:
企業特性と背景
- 登壇者による自己紹介から始まる
- 事業の特徴:
- 業界の変化が非常に速い環境
- 挑戦を好む社風(役員が若いことが特徴)
- IT部門がほぼ店舗出身者で構成
- データ量が多い産業的特性
- 400店舗、1000万SKUという規模
- 小売業特有のデータ豊富さ
内製化への道のり
- 2019年までの状況:
- 30年間、データ活用の仕組みも組織も硬直
- 基幹系システムからデータ抽出→職人技のExcelという流れ
- 内製化推進の第一歩:
- 内製化の恩恵とリスクを経営陣に丁寧に説明
- 中期IT計画で4つのシステム区分を明確化:
- 基幹系:安全性重視(責任取れないため外部委託)
- 管理系:効率性重視(強制的にパッケージ導入)
- 顧客系:拡張性重視(ローコード開発で内製&外注のハイブリッド)
- 情報系:機動性重視(変化の速い事業ニーズに追従する内製構築)
段階的なデータマネジメント構築
第1段階: Excel依存からの脱却
- 内製可能なBIを導入
- All-in-oneクラウドの内製導入
- データの共通言語化を実現
第2段階: データ活用範囲の拡大
- データウェアハウスを導入
- 当初2年分しか持てなかったデータの長期保持を実現
- 店舗とEC・マーケティング系のデータ統合
- 経営の意思決定高度化への貢献
第3段階: 顧客データの活用
- ExcelやAccessでは処理できない規模の顧客データ
- BIは固定レポート作成に適しているが自由分析には不向き
- 外部専門家との協業を通じて「データを分析する」感覚を習得
- データ分析専用のDWHと自由分析用BIの導入
第4段階: 専門組織の内製立ち上げ
- 情報システム部配下にデータ分析部門を新設
- これが「はまる」(成功する)
- 目標:「ビジネスをアジャイルできる情シス」の実現
内製データマネジメントの全体像
仕組み軸: 技術的アプローチ
- クラウドサービスの組合せで技術力不足をカバー
- 全体フロー:
- 発注・記録(kintone)
- 収集・変換(データスパイダー/ETC)
- 集計・演算(バッチ処理/JP1)
- 蓄積・成形(オラクル、BigQuery)
- 伝統的活用(BI)
- 近代的活用(AI、ML、MA)
- 重要な方針:「完全内製化は目指していない」
- ベンダーに依頼しても保守は内製化
組織軸: ユニークな体制
- デジタル本部内の3組織連携:
- ①情報システム部
- ②データインサイト室
- ③EC事業部
- 連携の仕組み:
- ①②はデータエンジニアリングで親和性
- ①③でOMO(Online Merges with Offline)促進
- ②から③にデータ分析支援提供
- 「稀有な組み合わせだが、当社にとっては最適解」
協業軸: 外部との連携
- 方針:「完全内製へのこだわりよりも、餅は餅屋に」
- 協業パートナー分類:
- 知恵袋:情報提供のみでSIを売らない企業
- クラウド事業者
- 内製支援専門企業
- 業務アプリ構築:「コスト<品質」の原則
実践から得た教訓
- リスクを適切に掌握できれば経営層は敵ではない
- 実務部門と肩を組めないとビジネスは変わらない
- クラウドを活用すれば人材不足は深刻な課題ではない
- 「とにかくまずはやってみないと何も始まらない」
参考:株式会社アルペン(企業Webサイト)
雑感
まずは、参加して本当に良かった!
このイベントは受講無料ですが、札幌在住者としては参加に数万円の投資(出張費)が必要です。参加するか数日考えましたが、終わってみれば十分すぎるぐらい元は取ったと思います。今回の学んだことは間違いなく仕事に生きてくるはずです。
スタッフ・関係者・会場やスポンサーのみなさま、有意義なイベントをありがとうございました!また来年も参加したいと思います。

ところで冒頭の「当日の10時間をどう過ごすことになるのか」の不安は残念ながら的中。密な部屋で40分じっと話を聞いた後、10分しかない休憩時間で “セッション後10分以内にアンケート(Web)への協力” を求められ “トイレは激込み” 。そして全セッション予約制のため “毎回総入れ替え” 。
カンファレンス系のイベントでは、過去イチ忙しかった気がします…
個人的には無料じゃなくても良いので、もう少しだけ時間と空間に余裕をつくってもらえると、とても嬉しいです!