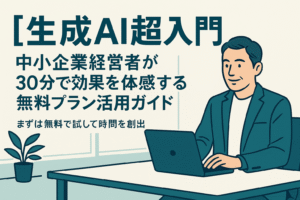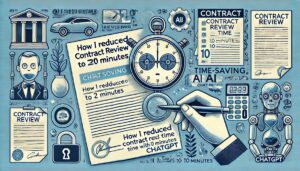議事録は作らない!Zoom+ChatGPTでサクッと記録(コスパ良く会議・商談を記録する)

正直、議事録はめんどくさいから作りたくない。とはいえ記録を残さなければ、後で言った/言わないでもめる。社内の会議であれば同じメンバーで再度話し合えば何とかなるが、お客様との商談だとそうもいかない。
なので会議を記録する必要性は理解できる。しかし、やっぱりめんどくさい。
ある調査1よるとビジネスパーソンは平均約320時間/年も議事録に費やしているらしい。しかも、その作成に負担を感じている人は67%もいるという。議事録がめんどくさいのは私だけではなかった!
このめんどくさいは、会議をZoomでレコーディングして文字起こしテキストをChatGPTで要約することで解決した。これまで作成していた議事録のように個人の努力(=メモや記憶)に頼るのではなく録音する。録音があれば後でもめようがないし、品質もあがって手間も減る。良いことしかなかったので共有します。
以下にあてはまる方は、ぜひ試してみてください。
- 社内会議が多く、議事録作成が大きな負担になっている企業・組織
- 商談や取引先との打ち合わせが頻繁にあり、内容を正確に残したい方
- 個人事業主・フリーランスで、顧客とのミーティング内容をしっかり記録したい方
- オンライン・オフライン問わず、より正確かつスピーディーな会議・商談記録を求める方
“がんばって”作る議事録の課題
まずは会議中にメモをとり、後でメモと記憶を頼りにまとめる、という従来型の議事録作成の課題を整理します。
課題1: 聞き逃し・書き漏れ
会議中に手書きやPCでメモを取る場合、どうしても発言の一部を聞き逃したり、話についていけず書き漏らしたりすることがあります(よね?)。特に会議が盛り上がると、アジェンダからの脱線も増え、後で振り返って「肝心なところをメモし忘れていた」ケースもありがちです。
課題2: 議事録を作る時間・手間
会議後にメモを整理して正式な議事録にまとめるだけでも、私の場合は余裕で1時間以上かかってました。ほかにやるべき仕事が山積みなのに、議事録作成に時間使ってる場合じゃありません。複数人で分担しても、結局は取りまとめ役に大きな負担がかかりがちです。
課題3: 表記ゆれ・書式が人によって異なる
複数人で議事録を作成すると、書き方や言葉遣いがバラバラになり、後から読み返しにくい。そこで議事録作成のルールを決めて統一しようとするのですが、最終的には取りまとめる人のセンスに委ねられてバラバラはなかなか解消されません。
課題4: 重要事項が埋もれてしまう
会議では多くの情報が飛び交うため、本当に大事なポイントが埋もれがちです。会議は「決定事項」や「次回までのアクション」を確認して終わるのが理想ですが、終わるころには疲れ果て、せっかく決めた重要事項の結論も確認からもれて議事録に残らないこともあります。
正式な議事録が重要な場面が多々あるのは理解できます。でも、すべての会議で形式ばった議事録を作るのはコスパが悪いと思います。
自動文字起こし+生成AI
これまでも手軽に会議を録音できましたが、後で聞き返しながら議事録を作るのは大変です。これをZoomとChatGPTで解決します。
どんな手順か
Zoomによるオンライン会議はレコーディングしておくだけで、音声や映像が保存されます。オフライン(対面)での会議であっても、(少々めんどうですが)Zoomを立ち上げてレコーディングしておきます。
Zoomにはレコーディングされた音声を自動で文字起こしする機能があります。会議後に少し(数分~数十分)まてば文字起こしされたテキストをダウンロードできます。
文字起こしテキストをChatGPTに入力します。まず整形し、そのあと必要に応じて要約します。要約は議事録の作成だけでなく、「○○についての話を要約する」など思い返したいトピックを軸にすることもできます。
試してみてどうだったか
- 想像していた以上に精度が良い
- 作業時間が一気に減る
- 聞き逃しや書き漏れがほぼゼロ
- 簡単に始められる
試してみると良いことしかなかったので、みんなやるしかない。
生成AI活用のメリット
先の課題それぞれに対して「自動文字起こし+生成AI」を使うと、どんなメリットがあるか紹介します。
メリット1:聞き逃しの防止
音声を自動文字起こしすれば、会議や商談の発言は後からいくらでも確認できます。メモに頼るだけでは抜け落ちてしまうような細かな情報も、録音や文字起こしをベースにすれば見落としが大幅に減ります。結果的に「言った/言わない」も起こりにくくなりますよね。
メリット2:時間・手間の削減
議事録の作成を生成AIに任せることで、会議後の負担は大きく減ります。空いた時間はお客様対応など本質的な業務に当てましょう。特に頻繁に会議や商談が行われる企業では、その効果をより強く感じられるかもしれません。
メリット3:品質の安定
生成AIによる要約を導入すれば、議事録の書きっぷりや表記を一定の形にそろえやすくなります。最初は試行錯誤が必要ですが、いろいろ試して読みやすい・理解しやすい形をテンプレート化しておくと便利です。
メリット4:重要事項の明確化
生成AIは、与えられたテキストから「決定事項」「タスク」「担当者」などをピックアップして整理するのが得意です。長い議論のなかで埋もれてしまいがちなトピックごとの結論や次回までの宿題なども、ひと目でわかる形にまとめられます。
その他のメリット
商談や取引先との打ち合わせでも活躍
「どちらが何を提案したのか」を正確にふり返れるようになり、後日見直したときにもスムーズに内容を確認できます。クライアントや協力会社とのコミュニケーションを整理するときに便利です。
スピーディーなナレッジ共有
会議内容をテキスト化して要約したものを、社内チャットや共有フォルダに載せるだけで、他のメンバーもすぐに情報をキャッチできます。キーワード検索を使えば、さらに意思決定のスピードアップにもつながります。
議事録を生成AIの入口にする
議事録以外にも、メールの文章作成やアイデア出しなど、生成AIを使う場面はいろいろあります。まずは議事録作成から試してみることで、社内のデジタル化やIT活用のハードルを下げるきっかけにしてください。
導入の簡単な流れ
ここからは、実際に「自動文字起こし+生成AI要約」する手順を紹介します。
社内会議を例に挙げていますが、商談や取引先との打ち合わせを録音する場合も、ほぼ同じ要領で進められます。
1. Zoomで会議をレコーディングする
オンライン会議なら
普段のZoom会議で「レコーディング」ボタンを押すだけ。映像と音声を同時に保存でき、さらに自動文字起こしデータが生成されます。
オフライン(対面)会議でも
オフラインでも、PCやスマートフォンでZoomを起動し、オンライン会議と同じくレコーディングします。ちょっといい会議用のマイクがあると、より正確に文字起こしされます。
ちなみに私が使っているのはJabra Speak2 55 スピーカーフォンです。コンパクトで、録音性能もそこそこ良くておすすめです。
2. 文字起こしデータの取得・整形(第1段階)
会議のあと数分から十数分するとZoomの管理画面から文字起こしのデータをダウンロードできます。ここで得られるテキストは、会議中の発言がそのまま時系列に並んだものです。
自動生成の文字起こしは生の会話状態
Zoomからダウンロードした文字起こしは、そのままだと読みにくいため、まずは会話の流れに沿って整形します。
以下は文字起こしのサンプルです。きれいに作られた議事録と違って話し言葉がそのまま並んでいて、まともに読めません。雑談は当然として、フィラー(あのー、えーと等のつなぎ言葉)もそのまま録音→文字起こしされるので、要約前にまずは整形しましょう。
WEBVTT
00:00:04.000 –> 00:00:11.000
田中: で、あの朝一番からすいません。スケジュール調整に時間かかってしまって。
00:00:11.000 –> 00:00:14.000
鈴木: いえいえ。うちの方も日程なかなか。
00:00:14.000 –> 00:00:21.000
中野: そうですね。まあ、これだけの方に集まっていただくので。
00:00:22.000 –> 00:00:24.000
田中: お疲れ様です。
00:00:26.000 –> 00:00:28.000
鈴木: じゃあこのまま。
00:00:28.000 –> 00:00:31.000
中野: はい、では本題の方に入らせていただきたいと思います。
00:00:31.000 –> 00:00:43.000
田中: はい、そうですね。あの、生成AIの活用について、なんでしょうか?っていうところで各部門からいろいろ声が上がってきてまして。
(以下、省略)
第一段階は、できるだけ詳細に
まずは作成されたテキストを「誰が」「いつ」「何を言ったか」が分かる程度に整理します。文字起こし時の誤字なども修正しながら、読みやすい形に整えます。
以下は、私がいつも使っているプロンプト(もちろん機密は削除)です。ポイントは手順[P1]で、最初に質問させることです。回答が手間ですが、出力の精度が上がります。あと音声を聞き直す場合にそなえて出力フォーマットにタイムスタンプを付けておくと便利です。
あなたは優秀な書記です。
添付ファイルは、私が携わっている #プロジェクト のZOOM会議音声の文字起こしです。
添付ファイルを読み込んで、以下の #手順 で整形してください。
#プロジェクト:
- 私(中野)はITコンサルタント
- 参加者は鈴木(スズキ)、田中(タナカ)、中野(ナカノ)
#手順:
[P1]#プロジェクト を理解した上で添付ファイルを読込み、不足している情報があれば質問してください
[P2]質問への回答で不足情報が補われてから、
編集者として文字起こしを要約せずに #出力フォーマット に従って整形してください
[P3]結果を表示する前に、制約に従っていることを確認してください
#出力フォーマット:
- テーマ (タイムスタンプ)
- トピック
- 詳細
- 詳細
- 詳細
- トピック
- 詳細
- 詳細
- 詳細
- トピック
- 詳細
- 詳細
- 詳細
#制約:
- 可能な限り要約せず詳細に出力する
上のプロンプトを実行すると、例えば以下のような質問が返ってきます。
[P1] 添付ファイルを読み込みました。この会議は生成AIの活用に関する検討会議のようです。以下の点について確認させていただきたいです:
- この会議は初回ですか、それとも継続的な検討の一環ですか?(「前回の続き」という発言がありますが)
- 画面共有されていた資料の具体的な内容(特に「三つの観点」や工程表、ベンダー比較表の詳細)について、もし補足情報があればお願いします。
- 経営会議での報告が言及されていますが、具体的な報告期限は設定されているのでしょうか?
これらの情報があれば、より正確な形で整理できます。現時点での情報でも整理は可能ですが、これらの点が明確になるとより詳細な整理ができると考えます。
これらについてご回答いただけますでしょうか?
質問に回答します。
1.継続的な検討の一環です
2.補足情報はありません
3.期限はありません
そうすると、以下のように文字起こしが整形されて出力されます。
ご回答ありがとうございます。それでは文字起こしを整形いたします。
[P2] 会議の内容を時系列に沿って整理します:
- 会議開始・導入 (00:00:04 – 00:00:31)
- スケジュール調整の謝辞
- 田中が朝一番からのスケジュール調整の遅れについて謝罪
- 鈴木も日程調整の難しさに言及
- 中野が参加者の多さに触れる
- 会議開始の合意
- 鈴木が開始を提案
- 中野が本題への移行を提案
- スケジュール調整の謝辞
- 生成AI活用の現状と課題 (00:00:31 – 00:02:40)
- 現状報告
- 田中が各部門からの声の増加を報告
- 鈴木が現場からの問い合わせ増加を確認
- 中野が整理状況を説明
- 検討事項の確認
- 前回からの継続検討事項の確認
- 三つの観点での整理を中野が提示
- インフラ面の検討必要性を鈴木が指摘
- パイロット導入の提案
- 中野がパイロット的取り組みからの開始を提案
- 田中が部門選定について現場の準備状況確認の必要性を指摘
- 鈴木がセキュリティ要件とシステム環境整備の必要性を指摘
- 現状報告
(以下、省略)
議事録のように要約されてませんが、会議や商談の記録としては十分ではないでしょうか。
3. 生成AIで要約(第2段階)
整形した文字起こしからさらに要約したり、議事録の体裁に整えたりしたい場合は、第2段階としてもう一度プロンプトを実行します。
ちなみに私はここまでやらない(必要性を感じない)ので、プロンプトのサンプルはありません。納得のいく形で出力されるまで、何度でもトライしてみてください。
4. 最終チェックと共有
生成AIの整形や要約は非常に便利ですが、誤変換や誤認識がゼロとは言い切れません。正式な議事録として扱ったり、商談相手に送付する場合は、必ず人の目で確認しましょう。私の場合は会議の備忘録程度の位置づけなので、ざっと見て誤変換くらいは放置します。
このように、レコーディング→自動文字起こし→整形→要約→議事録完成という流れを確立しておくと、どんな会議でも効率的に記録を残し、必要な情報をすぐに把握できるようになります。
補足:生成AI要約 vs Zoom AI要約
生成AI使わなくてもZoomのAI Companion 使えば?と思った方、その通りですが、自分で文字起こしから整形・要約した方がより柔軟に使えて便利です。
生成AI要約(ChatGPT・Claudeなど)
「文字起こしの整形だけする」「出力形式を指定する」「あるトピックだけ要約する」など、必要に応じて柔軟に出力できます。
Zoom AI要約(AI Companion)
会議終了後すぐにAIが要約を提示してくれます。要約だけでなく、会議の要点や「次のステップ」も作成されます。これはこれで便利。
導入時に注意すべきポイント
ここまで見てきたやり方は便利ですが、いくつか留意しておきたいことがあります。特にレコーディングや文字起こしデータの扱いについては、社内外のルールを確認しつつ進めましょう。
録音文化がない環境でのハードル
これまで会議や商談を録音してましたか?NOの場合、相手からの反発があるかもしれませんが、めんどくさがらずに必ず事前に了承をとりましょう。
特に社内や企業相手の場合は理解を得やすいと思います。個人顧客の場合は、時間をかけて丁寧に目的を説明するステップが必要かもしれないですね。
セキュリティとプライバシー
生成AIツールを活用する場合、文字起こし(テキストファイル)を外部のサーバーに送信することになります。特に機密性の高い情報を扱う場合は、使用するAIサービスの利用規約やセキュリティ対策をよく確認してください。
録音品質の確保
Zoomの文字起こし精度は、録音環境の良し悪しで大きく変わります。マイクが遠すぎたり音声が反響しすぎたりすると、誤変換が増える原因になりかねません。できれば会議専用のマイクを導入して、できるだけクリアな音声を記録できるようにしておくことが大切です。
最終チェックの必要性
自動で作成される文字起こしや、生成AIによる要約は便利ですが、細かい誤差が生じる場合があります。特に人名や専門用語、数値などは間違えると大きなトラブルにつながる可能性もあるので、最終的には人の目でざっと確認することをおすすめします。
まとめ
自動文字起こしを生成AIで要約する議事録(要約)作成は、手順自体がシンプルで、導入ハードルも低めです。これまでの議事録と比べて、作業時間を大幅に短縮できるほか、抜け漏れも減らせるなど、多くのメリットがあります。
まずは社内の小さな会議で試してみてください。(了承をとったうえで)同僚との雑談を録音して試してみるのもいいと思います。
社内のめんどくさいが少しでも解消されることを願っています。